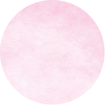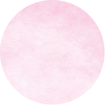MENU
CLOSE
| 産科・婦人科 | ||
|---|---|---|
| 9:00~ 13:00 | 16:00~ 19:00 | |
| 月 | 院長 雅子 智子 | 院長 雅子 智子 |
| 火 | 院長 雅子 智子 | 院長 雅子 智子 |
| 水 | 院長 雅子 智子 | 院長 雅子 智子 |
| 木 | 院長 雅子 智子 | 雅子 智子 |
| 金 | 院長 雅子 智子 | 院長 雅子 智子 |
| 土 | 当番医 | ー |
土曜日午後・日曜日・祝日は休診です。
| 小児科 | ||
|---|---|---|
| 9:00~ 13:00 | 16:00~ 19:00 | |
| 月 | 中山真由美 | ー |
| 火 | 横井順子 | ー |
| 水 | ー | 横井順子 |
| 木 | 坂田瑶子 | ー |
| 金 | 坂田瑶子 | ー |
| 土 | 当番医 | ー |
| 小児科 | |
|---|---|
| 9:00~ 13:00 | 16:00~ 19:00 |
| 中山真由美 | ー |
| 横井順子 | ー |
| ー | 横井順子 |
| 坂田瑶子 | ー |
| 坂田瑶子 | ー |
| 当番医 | ー |
土曜日午後・日曜日・祝日は休診です。